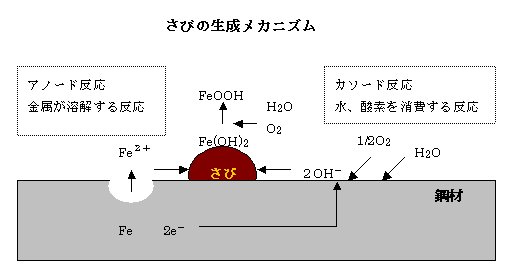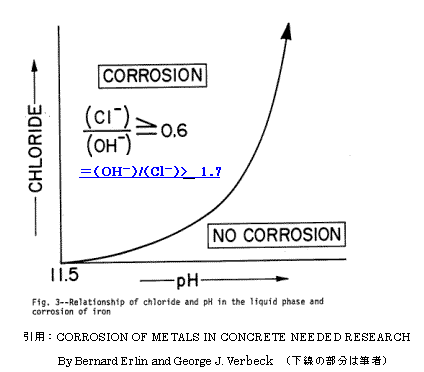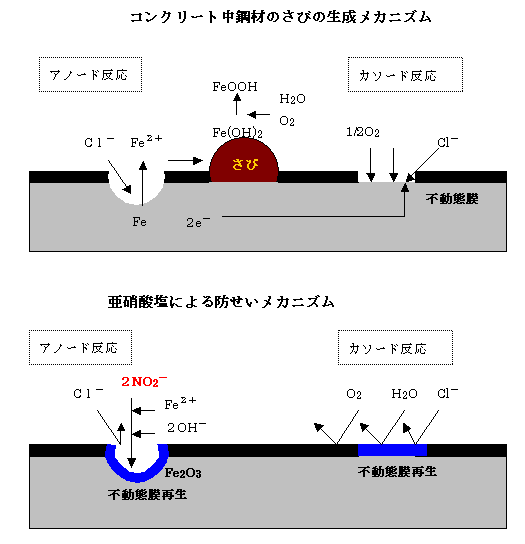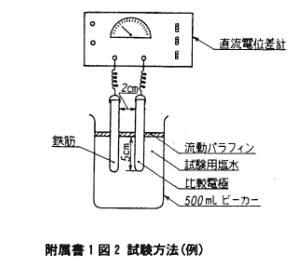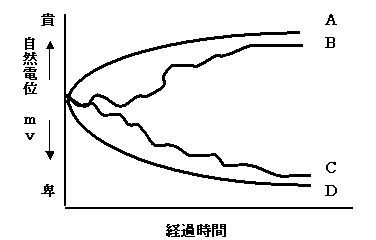|
|
| 第4部 防錆剤混和による鉄筋腐食対策 | 堀 孝廣 |
|
4-6 防せい剤とその作用機構 ここで、簡単にコンクリート用防せい剤とその作用機構について説明しよう。コンクリートはそのもの自体が、pH12以上の高アルカリ性環境にある。従って、通常の条件ではコンクリート中の鋼材は、防食環境下にある。そのため、コンクリート用防せい剤に関する研究は比較的新しく、ここ50年ぐらいのことである。長いような気もするが、コンクリート構造物に要求される耐久性から考えると、決して長いと言える期間ではない。日本での防せい剤の研究は、狩野春一、大島久次博士らが昭和29年から海砂使用に関するの研究を行なった時に始まる。両博士は、亜硝酸ソーダ、クロム酸カリの添加が防せいに有効であることを認め、特許を得ている。しかし、せっかくの特許も当時は海砂の使用も少なく、広範囲に実用化されることはなかった。昭和40年代の高度成長期に入り、海砂の使用が広がるとともに、防せい剤の研究も活発に行なわれるようになった。昭和48年には、岸谷孝一博士の指導により、沖縄県石川の火力発電所の建設に際し、日本で初めて防せい剤が本格的に使用された。当初、防せい剤としては、亜硝酸ソーダが使用されていたが、ソーダ(Na)塩であるとアルカリ骨材反応を起こす心配があるとの岸谷博士の指摘の下、日産化学では亜硝酸カルシウムの製造研究に着手した。当時、誰もアルカリ骨材反応についての注意を払わない中で、岸谷博士の先見性には驚く。亜硝酸カルシウムのコンクリート混和剤としての利用については、W.R.GRACE社が昭和42年に非腐食性の硬化促進剤として日本特許を取得しており、日産化学ではこのライセンスを受けて製造を開始した。海砂使用の広がりを受けて、昭和52年10月には、建設省住宅局の通知が出され、(財)日本建築センターは昭和53年3月2銘柄の防せい剤に性能評定書を交付した。昭和57年には、JIS A 6205(鉄筋コンクリート用防せい剤)が新規に制定された。この当時、防せい剤を使用したコンクリートは、年間150~200万m3に達している。その後の経緯については、既に触れてきた通りである。 防せい剤としては、前記の亜硝酸塩、クロム酸塩のほか、リン酸塩、ケイ酸塩、リグニンスルホン酸カルシウム、安息香酸塩、アミン類などが単独で或いは複合状態で研究されてきた。クロム酸は効果に優れていたと言うが、現在は重金属であるため使用されていない。亜硝酸塩を除くその他の殆どの化合物も、防せい効果が不十分であったり、コンクリート中の強アルカリ環境下での安定性や、セメントの凝結に与える影響に問題があったりなどして使用されていない。現在、コンクリート用防せい剤としては亜硝酸カルシウムが大部分であり、一部アミン類が使われている。また、コンクリート補修用には、次節で紹介する亜硝酸リチウムが使用されている。 さて、次に防せい剤の作用機構について説明しよう。さびは以下に示す電気化学反応として、進行する。
アノード型防せい剤は、金属が溶解する部分を封鎖してしまうタイプの防せい剤であり、溶解する部分に不動態皮膜を形成しさびを防止する。亜硝酸塩系防せい剤はこのタイプに属する。一般にアノード型防せい剤は、金属が溶解する部分だけを抑えれば良いので、少量で良く効くとされるが、量的に不足したときに孔食を起こすことがあるとされている。しかし、コンクリートが強アルカリ性のためか、防せい剤の使用によって腐食が促進されたという事例は報告されていない。 カソード型防せい剤は、水、酸素が接触する金属表面全てを覆う必要があり、充分な効果を出すためには、たくさんの量を必要とする。ケイ酸塩や炭酸塩、リン酸塩はこのタイプの防せい剤である。 アミン系防せい剤は、金属表面に吸着する機能を持っており、アノード、カソード両部の反応を同時に抑制すると言われている。10年ほど前にアメリカのマスタービルダーズ社、スイスのSIKA社がこのタイプの防せい剤販売を発表したが、広範囲に普及するまでには至っていないようである。防せい剤は、構造物の耐久性に直接影響してくるので、コンクリートの強アルカリ性の中で、薬剤そのものの安定性が問われる。新しい防せい剤は、なかなか登場しにくい環境にある。 コンクリート中の鋼材は、通常は不動態膜に覆われ、腐食から保護されている。これが、中性化する或いは塩化物イオンが侵入してくると、不動態膜が破れ腐食が進行する。アルカリ性環境下で、腐食が発生する塩化物イオン濃度とpHとの間には。以下の関係があるとされている。
細孔溶液中のOH−濃度は、0.6モル程度であるから(Cl−)/(OH−)=0.6となる塩化物イオンは、0.36モルとなる。コンクリート中の水の量を概略100リットル/m3とすると、1.3kg/m3となる。少し塩化物イオン濃度が高すぎるような気もするが、水溶液とコンクリートとの条件の違いを考えれば、妥当な数値と判断できる。 コンクリート中の鋼材の塩化物イオンによる腐食と、亜硝酸塩系防せい剤の防せいメカニズムについては以下のように説明されている。
コンクリート中で、塩化物イオンは不動態膜を溶解し、孔食を発生させる。 亜硝酸イオン(NO2−)は、溶解してきた鉄イオン(Fe2+)と反応し、破壊された不動態膜を再生する機能を持っている。不動態膜は、塩化物イオンによる破壊と亜硝酸イオン、水酸化物イオンによる再生の競争反応下にある。塩化物イオンがまされば腐食が進行し、亜硝酸イオンがまされば腐食は抑えられる。 ここで、モル比(イオンの数の比)が重要となってくる。FHWAのY.P.Virmaniや筆者らの試験で、防せい効果を維持するためには、亜硝酸イオン/塩化物イオンのモル比で1.0以上が必要としたのは、このような理由によるものである。 それでは、不動態膜が再生されたかどうか、どうやったら確認できるのだろうか。不動態膜の厚さは数オングストロームと極めて薄く、肉眼や電子顕微鏡などによっても確認は難しい。ここで、活躍するのが電位測定という手法である。JIS A6205『鉄筋コンクリート用防せい剤』の付属書1にも、鉄筋の塩水浸せき試験方法として掲載されている。
JISのこの試験を厳密に行なおうとすると、鉄筋の加工、試験用塩水と流動パラフィンの接する界面の処理などたいへん難しいが、およその傾向をみるだけなら試験液の中に鉄筋と比較電極(pH測定用の銀塩化銀電極で良い)を差込み、mVまで測定できるデジタルマルチメーター(電気店で1万円ぐらいで手に入る)をつなげば良い。結果は、以下のようなパターンになる。
以上、水溶液試験の代表的なパターンを示したが、コンクリート中に埋め込まれた鋼材についても適用でき、腐食条件下にある鋼材に防せい剤が浸透していき、あるモル比になると電位が貴に向かい、防せい効果を確認することができる。 |