第8章 基 礎(地盤の力学)
|
8.6 深い基礎
|
初期の技術者は、失敗や成功を繰り返したその経験の中から、構造物の真
下の地盤が軟弱であったり、圧縮性の高い土である場合は、基礎を地中に深
くおろして、支持力のある地盤へ連結させねばならないことを知った。そし
て、この要求に合致する深い基礎の形態として、次の二つがよく用いられた。
すなわち、比較的細い柱を地表から打ち込む杭基礎と、重い荷重を支える
ときに、割合安価になる地盤を掘削して施工するピア基礎とである。しかし
最近は、杭にも、いろいろの改良型が現われてきたし、またケ−ソンを初め
とする。各種の工法が数多く考案され、深い基礎の工法は、一段とその進歩
発展が見られるに至った。
|
 |
|
 |
8.6.1 杭基礎
(1)杭の種類
杭は、その機能から分類すると、図−8.25のごとくで、
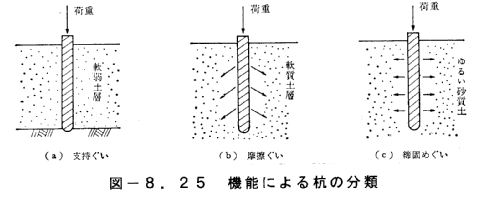
(a)支持杭
上部構造の荷重を、やわらかい層を貫いて、その下の岩盤や堅い地盤に広
げて伝えるので、構造的に、杭は長柱として働く。最もよく用いられる型の
杭である。
(b)摩擦杭
杭の側面と、地盤との間の摩擦によって、構造物の荷重が地盤に伝えられ
るもので、(c)の締固め杭とともに、堅い地盤が非常に深い所にある場合に
活用される。
(c)締固め杭
一群の摩擦杭を地中に打ち込み、杭の間の土層を締固めて、その摩擦支持
力を増加せしめ、構造物の荷重を支えるもの。
また、杭に使用する材料や施工法によって分類することもあるが、理解を
助けるため図−8.26にそれを示した。
(2)杭基礎の許容支持力
杭基礎が破壊せず、過大な沈下も起こさず荷重を支える能力は、次の三つ
の要素で決まる。
(a)杭が長柱として働く強度
(b)杭が、その荷重を下部あるいは側面の土へ伝える能力
(c)杭の下および側面の土の強度と圧縮性
支持杭は、頂部と先端が固定された柱で、地盤中に打ち込まれたときは普
通、完全支持の短杭として設計する。しかし、やわらかい粘土層中の杭、あ
るいは水中や空気中に露出した杭は長柱として働くので、座屈破壊に注意し
なければならない。
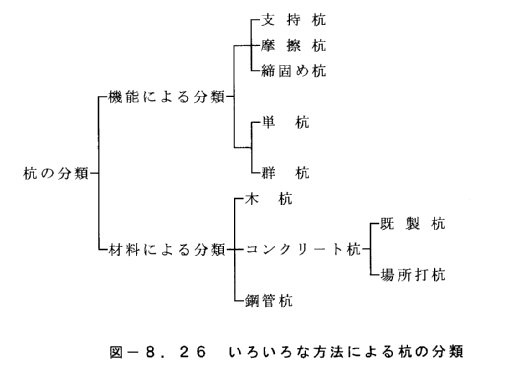
杭が、構造物の荷重を地盤に十分伝え潤香どうかは、杭基礎としては最も
大切なことである。杭は、土の支持力以上の力でたたき込まれるから、土は
杭直径の1~2倍の広さにわたって乱され、鋭敏比の高い粘土では支持力の
低下、砂質土では内部摩擦角の変化を引き起こす。そして、その強度が元へ
戻るには数か月を要することもある。しかし、ジェットやドリル工法で打ち
込まれる杭は、土の乱される領域がもっと狭くなり、10cm前後に止まるこ
とが多い(図−8.27(a))。
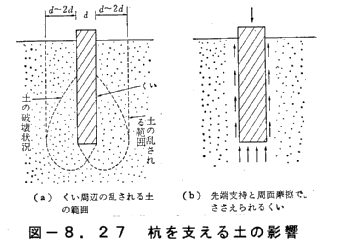
杭の支持力を算定するには、図−8.27に示されるように、岩、砂、堅
い粘土で支えられる先端支持力と、杭の側面の摩擦や、せん断抵抗の合計で
計算する静的杭公式がある。その一例は、(8.20)式に示すとおりであるが、
先端支持力は、(8.4)式 の正方形基礎の支持力公式を用い、一辺を0.9D(
D:杭直径)と置き換えて近似計算すれば求まる。また周面摩擦は、粘性土
の場合は粘着力から求まり、砂質土の場合は、杭面に働く有効垂直圧力と摩
擦係数(表−8.5参照)の積で求められる。
Qc=Qp+Qf ・・・・・・・・・・・(8.20)
ここに、Qc:杭の限界支持力(t)
Qp:杭先端の支持力(t)
Qf:杭周面の支持力(t)
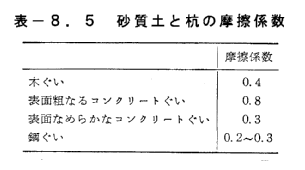
静的公式は、特に、杭の長さを決定するときに有用である。
また、支持力公式としては、杭の打ち込み時の抵抗から支持力を算定する
動力学的公式がある。
動的公式は砂質地盤に対しては、比較的正確な値を与えるといわれ、どの
公式も、ハンマ−または錘のもっている機械的エネルギ−が、杭や土に伝え
られるエネルギ−に等しい、という考えから成り立っている。すなわち、R:
貫入抵抗、S:1打撃の貫入量、Wr:ハンマ−の重量およびH:ハンマ−
の落下高とすると、次の公式が成立する。
R×S=(Wr×H)−(エネルギ−損失)
このような考え方で整えられた公式として、よく用いられるものに、次の
二つのものがある。
<エンジニヤリングニュ−ズ公式>
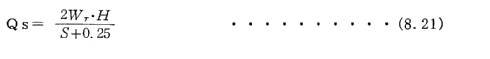
単働杭打ちハンマ−使用
<ハイリ−の公式>
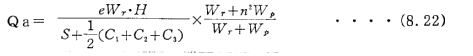
ここに、Qs、Qa:杭の安全支持力(kg)
Wr:ハンマ−の重量(kg)
H:ハンマ−の落下高(m)
S:ハンマ−1回の打撃による沈下量(cm)
e:ハンマ−の効率
Wp:杭の重量(kg)
n:衝撃の点における、杭のもどり係数
C1,C2,C3:それぞれ打ち込み時におけるキャップ、杭の長さおよび地盤の一時的な変形量(cm)
(3)杭の許容沈下量
杭基礎の許容沈下量歯、三つの観点から決められる。
(a)載荷中の柱としての弾性変形。
(b)杭周辺の土の弾性変形。
(c)杭直下の土の圧密。
後の二者は、直接基礎の沈下と同じように考えることができる。(a)の問
題は支持杭の場合、その全長について計算するが、摩擦杭の場合は、その長
さの1/2~1/3について計算すればよい。
(4)群 杭
フ−チングや基礎の下の杭は、よく接近して打ち込まれるから、群杭とし
て考えるのが適当である。この考えは、杭が、純粋な摩擦杭である場合、お
よび圧縮土層の下の堅い層に支持杭として支えられている場合などでは、と
くに重要である。群杭の支持力は、図−8.28に示すように、ほぼ、杭の
先端を底面とする大きいフ−チングと考えて、底面の支持力と周面のせん断
抵抗の和で計算すればよい。すなわち、
Q=Qb+A・τf
ここに、Q:群杭の支持力(t)
Qb:仮定フ−チングの先端の支持力(t)
A:仮定フ−チングの全周面積(㎡)
τf:杭と土との間に働くせん断強さ(t/㎡)
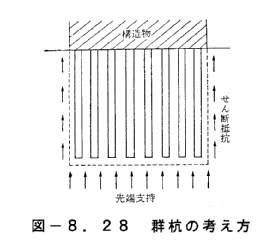
群杭の間隔は、単杭の支持力の総和よりも、群杭の支持力が大きくなるよ
うに設計すべきであるが、これが必ずしも簡単でない。純粋な摩擦杭のとき
は、、(群杭の周面積)≒(単杭の周面積の合計)になるよう間隔を取るの
がよいが、その他の場合は、(群杭の周面積)<(単杭の周面積の合計)の
ことが多い。また、杭の直径をDとすると、一般の場合、(適当な杭の間隔)
>2.5D あればよく、4D以上では不経済になる。
群杭の沈下は、杭先端より下の土層の圧密によって生じ、これを支える堅
い土層が下にない限り、同じ荷重を支える単杭の沈下より大きくなるのが普
通である。したがって群杭の沈下は、群杭の大きな基礎として解析される。
すなわち、杭が先端支持である場合は、図−8.29(a)に示すように、杭
先がそろっていれば、杭先を底面とするフ−チングとして応力分布を計算す
る。また、摩擦杭のときは、図−8.29(b)にみるように仮想基礎底面が
杭長の2/3 の深さに合って、全底面に荷重が等分布するものとして、基礎下
の応力と沈下を求めることができる。
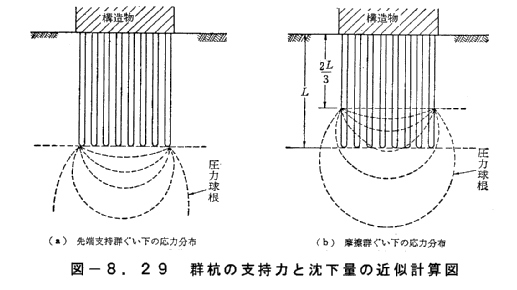
|
 |
|
 |
8.6.2 ピア基礎
ピア基礎というのは、比較的その規模が大きく、かつ深い基礎のことであ
る。杭基礎とのおもな相違は、寸法(杭の直径が50cmを越すとピアと呼ぶこ
とが多い)、およびその建設方法にある。
杭は地表からそのまま打ち込むが、ピアは大型であるため、ほとんど掘削
しながら施工する。
ピアをその工法で分類すると、図−8.30のようになる。
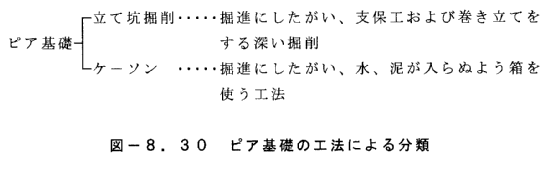
ピア基礎に使用する材料や工法は、加わる荷重、地下水の状態、主として
荷重を支える層の深度、建設規定、および機材の利用性などから決まる。ま
た、ピアが水中にはいる可能性があれば、流速・浸食を受ける深度および氷
や岩屑の影響なども考えねばならない。
(1)ピア基礎の支持力と沈下
ピアは、その先端支持力と、周面のせん断抵抗で支えられる大型のフ−チ
ングであるから、支持力や沈下を考慮するにあたっては、これらに対する検
討が必要である。
先端支持力は、普通のフ−チングに根入り土圧が加わるとして計算すれば
よい。周面の抵抗は、周面摩擦として知られているが、量的には小さいもの
である。粘性土の粘着力は、乱さない土のせん断試験で求め、砂質土の摩擦
抵抗は、(ピアに対する土圧)×(摩擦係数)で求めればよい。この土圧は、
静止土圧を採用すべきで、摩擦係数は表−8.5を参照するとよい。
ピア基礎の沈下量も、だいたいフ−チングの沈下量計算法を応用すればよ
いので、砂質土では載荷試験を行なって推定し、粘性つちの沈下量はウエス
タ−ガ−ド(8.14)式からΔσz を求め、接触沈下量と圧密沈下量を合計して
求める。
(2)立て坑掘削
簡単なものは浅掘りの井戸と同じで、手や大きなオ−ガ−で掘り、井枠を
組ながら掘進する。所定の深さまで掘削し終われば、これをコンクリ−トで
埋める。オ−プンウエルは、地下水位より上の堅い粘性土には適するが、7
mより深くなると切張りなしには施工できない。立て坑掘削の一例として、
図−8.31に古くから用いられている深礎地業の工法略図を示す。
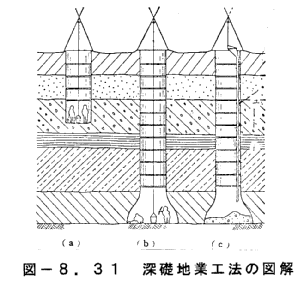
(a)定規井わくを基準にして掘削し、掘った土は、三脚やぐらに取り付けた
バケットで坑外に搬出する。
(b)支持地盤に達したら支持力を測定し、所要の大きさに掘り広げる。
(c)底部へコンクリ−トを打ち込み、大きい礎段をつくる。
(3)ケ−ソン(潛函)
ケ−ソン工法は、地上または地中につくった構築物を、その下の土を掘削
しながら自重により沈下させ、地中に基礎をつくるもので、オ−プンケ−ソ
ン工法とニュ−マチックケ−ソン工法とがある(図−8.32参照)。
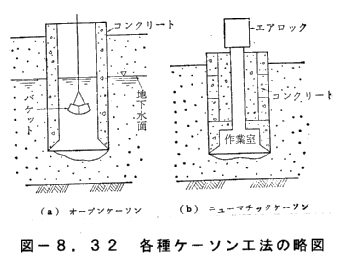
オ−プンケ−ソンは先端に刃先を有する函で、岩盤に達するまで排水しな
いのが普通であり、橋脚の建設によく用いられる。
ニュ−マチックケ−ソンは、オ−プンケ−ソンでは施工が困難な場合に用
いられる。気密な天井、壁を用い、圧搾空気を送り込んで作業室の気圧を高
めて、水や泥の入るのを防ぎながら掘削する。ロックから作業室への出入り、
圧力の調整、およびケ−ソン病の問題など、ニュ−マチックケ−ソンの使用
にあたっては、多くの難しい問題があるから、経験のある技術者がその設計・
施工を企画しなければならない。
<参考文献:箭内他、土質工学、わかり易い土木講座6、彰国社刊>
|
 |
|
|
[ ↑目次へ戻る ]
|
 |
