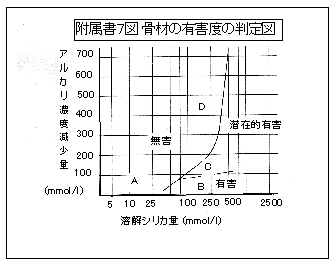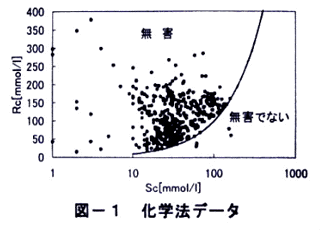|
|
| 第2部 アルカリ骨材反応 | 堀 孝廣 |
|
2.4 アルカリ骨材反応のメカニズムその2 アルカリ骨材反応のメカニズムを、骨材のアルカリシリカ反応性試験の化学法をもとに考察してみよう。以下に化学法の判定図を示す。 化学法は、150~300ミクロンに粉砕した骨材25gを密閉容器にいれ、1NのNaOH溶液25mlを加え24時間80℃に保管・反応させて、溶け出したシリカ量と反応に消費されたアルカリ量を測定するものである。その結果を判定図(例JIS A 5308の附属書7図)に挿入して、有害性を判定するものである。
図中に記したA,B,C,Dの点について考察してみよう。 A点は、溶解シリカ量も少なくアルカリ消費量も少ない。これは反応性が低いことを表している。 B点は、アルカリの消費量は少ないが、溶解シリカ量が多い。これは、反応生成物のSiO2/Na2Oのモル比が高いことを表している。このような高モル比のアルカリ−シリカ化合物は、水に溶け難く、またカルシウムイオンの影響を受けてゲル化し易いため、骨材表面で反応ゲルを蓄積し易すい。D点は、溶解シリカ量も多いがアルカリ消費量も多い。ここでの反応生成物は、低モル比のアルカリ−シリカ化合物が生成していると考えられる。シリカ1分子当たりのアルカリ量が多くなるほど、カルシウムイオンに対してタフになり、ゲル化しにくくなる。従って、このような高モル比のアルカリ−シリカ化合物は、骨材表面からコンクリート中に溶解状態で拡散し、骨材表面にゲルを蓄積しにくいものと考えられる。C点は、B点とD点の中間的性質を示す。しかし、この図で注意しなければいけないのは、D点で無害と判定された骨材についても反応生成物がゲル化しないわけではなく、条件によっては骨材表面でゲルが蓄積し膨張を引起こす可能性があることである。 事実、今年(2001)の土木学会の年次学術講演会では、JR東日本の松田氏によって、化学法による膨大な点数のデータ(下図)が報告され、無害と無害でないの境界線付近に多数の骨材が分布し、昭和61年のJISの制定以降も、アルカリ骨材反応を生じた事例が時々発生していると報告されている。
|